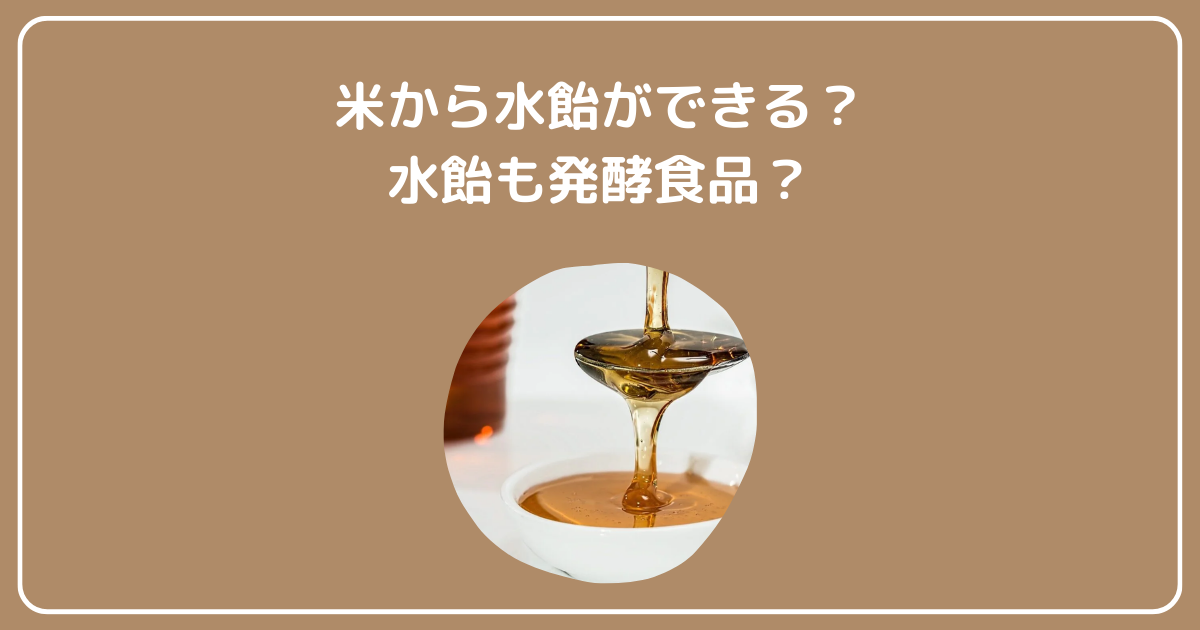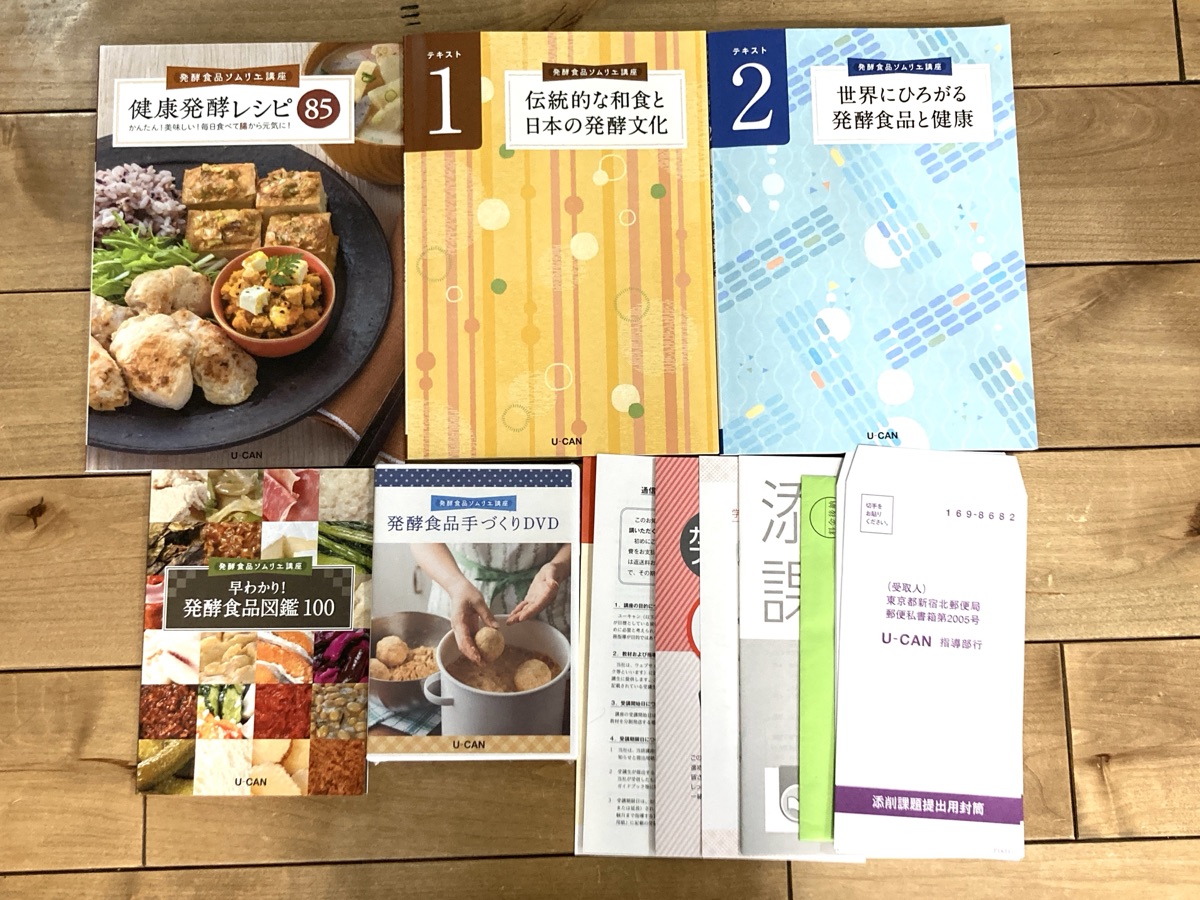水飴(みずあめ)は、そのまま飴として使われたり、お菓子や料理に調味料として用いられます。
今のように砂糖が主流になる前の時代は水飴が主要な甘味料でした。
最近知ったのですが水飴と呼ばれるものは米や芋などから作られているそうです。
でも米からどうやって飴ができるの?と思い、調べてみると発酵に近い作り方をしていることが分かりました。
水飴はデンプンを酵素で分解して作る
水飴は、米、芋、もち米などに含まれているデンプンを分解して作ります。
デンプンはブドウ糖がたくさん結合してできたものですので、デンプンを分解すると麦芽糖やブドウ糖などの糖分が切り離され甘味を感じるようになります。
このデンプンを分解するのに必要なのがアミラーゼなどの酵素です。
- 水飴は米などに含まれているデンプンを分解して作られる
- 分解に必要なのがアミラーゼなどの酵素
酵素は麦芽や発芽玄米などに含まれている
デンプンを分解するのに必要な酵素は、麦や玄米を発芽させたものに多く含まれています。
これらは麦芽や発芽玄米と呼ばれます。
ちなみに麦芽といえばビールの原料として有名ですがこれも麦芽に含まれる酵素を利用するためです。
水飴の作り方
材料:米3号、麦芽100g、水500mL
炊いた米に水を混ぜ、50~60℃位で麦芽を混ぜます。
ヨーグルティアなどでそのまま温度を保った状態で一晩置きます。
ドロドロになるので、こした汁を煮詰めると完成です。
参考レシピ:まぜて一晩放置!麦芽でつくるカラダにやさしい米飴 レシピ・作り方(rakutenレシピ)
味噌作りにも同じ過程
米を酵素で分解する過程は味噌作りにもあり、米が麹の酵素で分解され甘味が増えるのと同じメカニズムです。
昔の人は酵素なんて知らないはずでしょうから、たまたま炊いた米に発芽玄米が混ざって甘くなることを発見したのでしょうね。
見えない酵素を上手に使いこなしていた昔の人は凄いです。